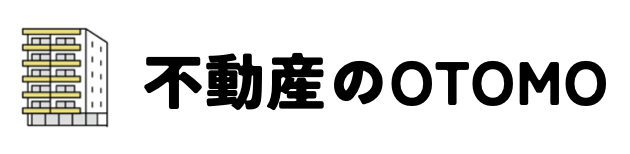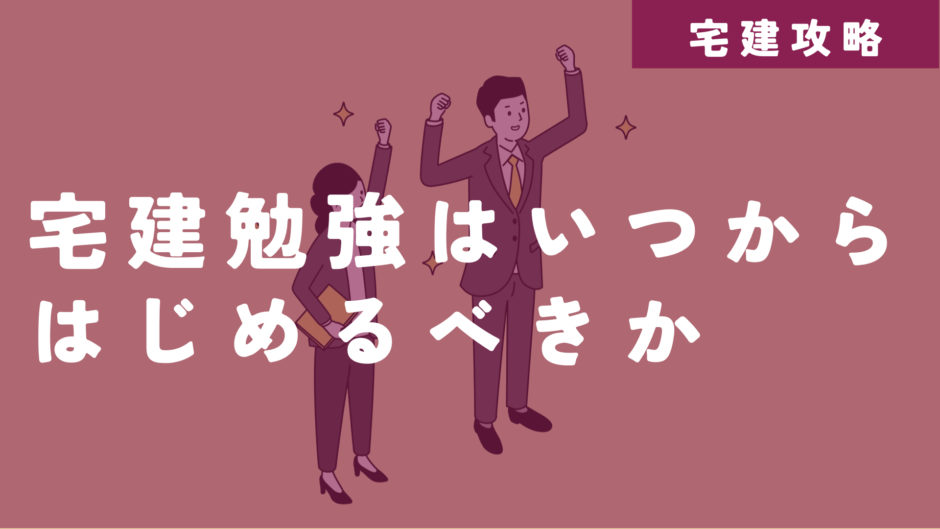宅建の勉強はいつから始めるべきですか?
宅建を受けてみようかな?宅建を必ず取らなければならない。
色々な気持ちの方がいらっしゃると思います。
いきなり厳しい言葉になってしまうかもしれませんが、私が言えることは、受験を決めたその日から勉強を始めるべきということです。
宅建は国家資格の中では簡単と言われますが、それでも国家資格であることに変わりはありません。
国家資格に合格するということは、特定の業務を行なっていいですよ、という証明になるのです。
なので、甘い資格ではありません。
かくいう私は、1回目はどこかでそのような気持ちがあり、2点足らずで不合格になりました。
気持ちを改め、1年間本気で取り組んだ結果、2回目の試験で40点を超えることができました。
1回目・・・6月受験開始で10月に受験。2点不合格。
2回目・・・1年前から勉強開始。結果、専門学校の全国模試で3、000人中11位。40点越えで合格

私自身振り返って、1日でも早く始めるべき、と言えます。
そうはいっても、闇雲に勉強するのは得策とはいえません。
今回は、受験を決めたその日から何をするか?
そして、この記事を見ていただいているのが、試験日から逆算してどのぐらい前か?
で戦略が異なりますので、是非そのような疑問を持たれている方のために解説してみます。
宅建試験について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
目次
初めて宅建を受ける場合
初めて宅建を受ける場合に知っておくこと。
それは、以下の3つの受験スタイルを決めることです。
- 予備校に通う
- 通信講座を取る
- 独学で勉強する
予備校や通信講座は、その期間に沿って行えば良いと思います。

予備校や通信講座は高いし、できるだけ独学で勉強したい・・・
今回は、そのような、主に独学で勉強する方を対象に解説します。
そして、宅建は独学で受かることが可能な試験です。
独学で受ける場合は、試験日から逆算して今どのぐらいの時期か?を意識することが必要です。
宅建の勉強は300時間が目安とされていますが、これは独学の場合、もっと多めにみておいた方が良いでしょう。
最初は、必要のないテキストを余分に買ってしまったり、不要な情報を学んでしまったり、と回り道をしてしまうためです。
こちらの記事も参考にしてみてください。
宅建合格に必要な勉強時間は300時間はウソ?うのみにすると失敗します
宅建の時期別、独学の勉強方法の基本
独学の勉強方法ですが、基本は以下の流れです。
- 過去問を解く
- 基本のテキスト集を見る
- ①と②の繰り返し
- 模試を解く→弱点を出す→その分野を集中して解く→模試を解く
- 本番
まずテキストを読んでから、ではなく、過去問→テキストの反復の流れを守りましょう。
答えがわからなければ、解説をみながら、どんどん進めていきましょう。
私の場合は、LECさんの問題集を使いました。
一年目の受験の時は、色々な問題集に手を出しすぎたのも不合格になった原因の一つだと思っています。
実際に、どのように問題集を使えば良いのか?は以下の記事をご参考ください。
それでは、時期に合わせた勉強法や注意点を解説していきます。
宅建試験日1年前(残360日)から始める場合
1年前から始める方は、じっくり取り組むことができます。
1日1時間で360時間です。
この時期から始める方は権利関係(民法)に注力することをお勧めします。
なぜなら、民法は暗記科目ではなく、理解することが必要で、暗記科目のようにすぐに正解を導き出すことができません。
この時期から始める方は、民法を優先的に進めておくことで、他の方と比べて優位に立てると思います。
あまり勉強時間を意識しすぎず、ページ数・問題数で進めていくことをお勧めします。
例えば、LECのウォーク問を例に挙げると、1冊で約150問あります。
1日10問、などと決めてやると、実質15日で1周が終わります。

勉強時間にとらわれすぎず、何ページやる、という具体的な目標を決める方がスケジューリングしやすいです。
1日5問だと30日で終わりますので、2ヶ月もあれば2周が可能な計算になります。
そして、このときに必ず○だったか×だったかを記録しておくことが重要です。
この後説明する直前機に大いに役に立ちます。
半年ほど宅建試験に慣れ親しんでいると、この頃にはだいぶ理解が深まってきます。
しかし、この時期に気をつけておきたいことがあります。
それは、最初にやったから後は手をつけない、とすると記憶はどんどん薄れていきます。
ドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスが発表したエビングハウスの忘却曲線によると、何かを学ぶと人は31日間経つと79%忘れると言われています。
ここでそれぞれ1周ずつ回したり、模試を受ける、というのは全体的にどの部分が弱いか?という点と、記憶を繋ぎ止めておくという2点の狙いがあります。
9月:模試を受けて、自分の弱い部分を知り、部分的に徹底して復習する。絶対に落としてはいけない分野の問題を復習する。
模試は必ず受けましょう。
出来るだけ、自分の慣れしたしんだ問題集があれば、そこの模試がベストです。
私は、LECの問題集なので、LECの模試というようなイメージです。

気付いたら模試の締め切りが終わっていた、、というようなケースもあるので、要注意です。
できれば、会場受験をお勧めします。
理由は、試験に近い雰囲気を味わうことと、実際の時間配分をシミュレーションすることです。
加えて、模試の点数は気にしなくて良いです。
一番気にすべきは、宅建業法と法令上の制限の点数です。
民法は、クセのある問題が多いですが、宅建業法と法令上の制限は、模試であっても、ある程度点数を取っておきたい部分です。
解いてみて弱点だな、と思う分野であれば、再度その分野を集中して復習し、その翌週に模試を受ける、といったやり方もあります。私はそうしていました。
この時期は、緊張やプレッシャーもピークですが、一番点数が伸びる時期ですので、無理をしすぎない程度に頑張りましょう。
10月:これまでやってきて、間違えた部分の再復習を行う。何度も間違える部分のみ復習する。
最後は、これまでやってきた自分の総まとめです。
最初に、必ず○だったか×だったかを記録しておくことが望ましいと述べましたが、この時期は×のところで、毎年必ず出るテーマを中心に繰り返します。
そして、スキマ時間は全て宅建の勉強に充てる方が良いです。
電車の時間はもちろん、運転中や移動中、お風呂の中など、Bluetoothイヤホンなどを使ったり、宅建関連のYoutubeなどを見たりして、常に宅建に触れている時間を増やしましょう。
とにかく受かる!!気持ちがとても大事です。
宅建試験6ヶ月前(残180日)から始める場合
前章では1年のスケジュールを説明しました。
6ヶ月前、4月から勉強を始められる方も多いでしょう。
ざっくり言えば1日2時間で360時間程度の勉強時間を確保できます。

1日2時間と聞くと大変そうに思えるかもしれませんが、細切れの時間もかき集めて、平均2時間は確保していただきたいところです。
スケジュール感で言えば、先ほど説明した1年スケジュールを2倍速でこなすイメージです。
ここで先ほど説明した◯×の記録が役に立ちます。
苦手な点を集中して復習していきましょう。
宅建試験3ヶ月前(残90日)から始める場合
現実的に、この3ヶ月前というのが、合格に間に合うリミットかなと思います。
1日3〜4時間は勉強に充てる必要があります。
この時期から始める方は、注力する分野を選ばなければなりません。
思い切って民法は捨てて以下の分野に注力しましょう。
- 借地借家法
- 区分所有法
- 不動産登記法
- 宅建業法
- 法令上の制限、税・その他
- 5問免除
民法以外の分野を極めることで、40点近く行きます。
民法に時間をかけない理由は、勉強したところが必ず出るとは限らないからです。
3ヶ月という期間では、どこを捨てるか、ということが非常に重要になってきます。
思い切って民法を捨てて、その他の分野を倍速でやりましょう。
3ヶ月前までは以上の通りですが、あとは本番直前。
緊張がピークに達する頃ですが、これまでやってきた努力を信じて、やっていきましょう。
実力が一番伸びる時期です。